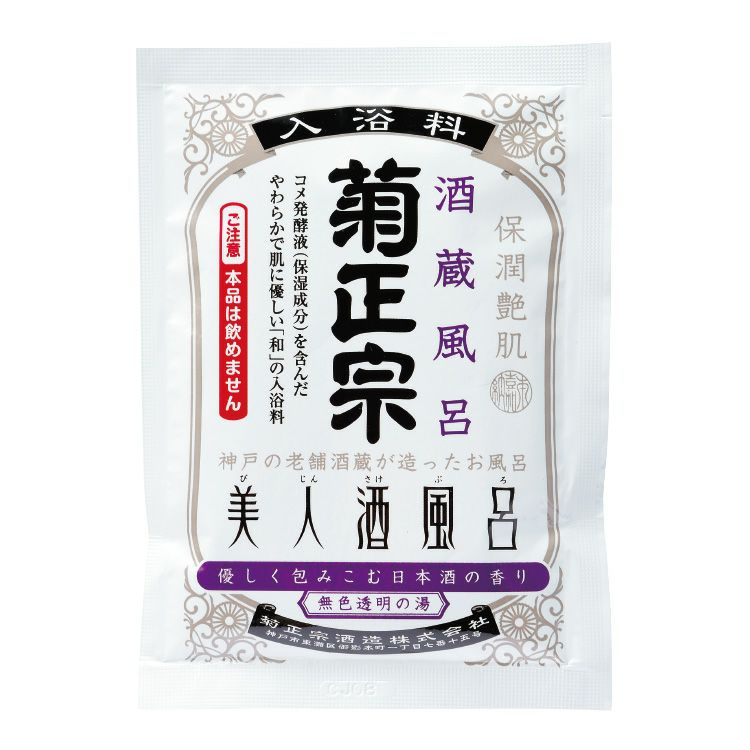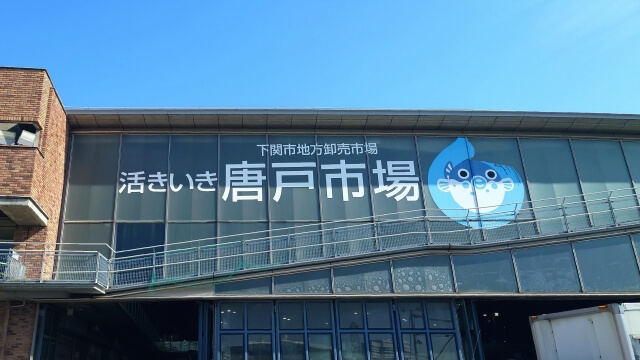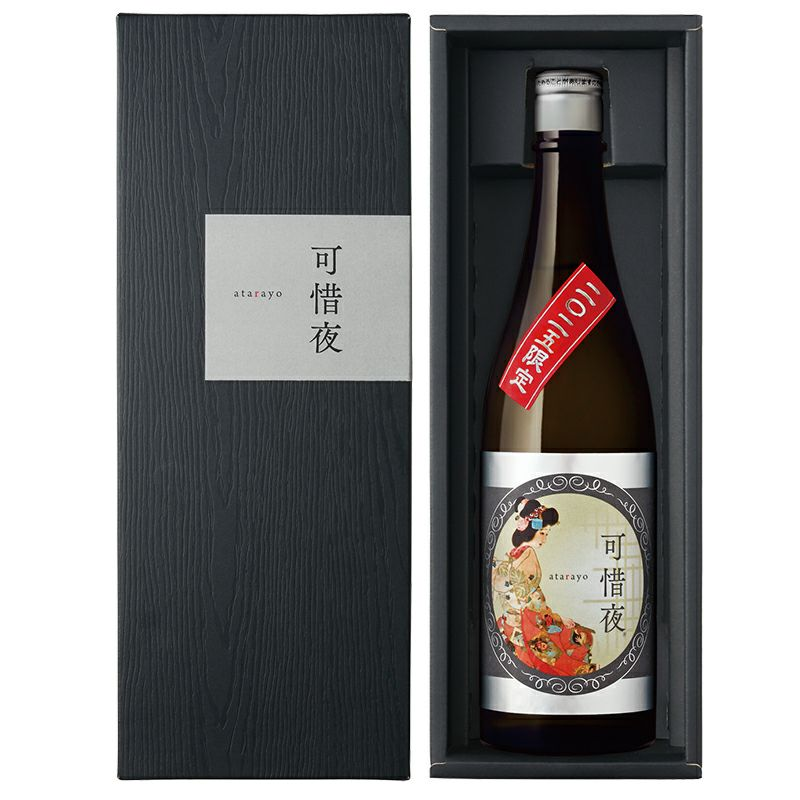煩悩を払い、新しい年を迎える日本の伝統。
最近は除夜の鐘を騒音と感じる方もいるようで、長く続く伝統文化も時の流れの中で少しずつ薄れているように感じます。除夜の鐘といえば、凛と冷え込んだ大晦日の夜に響く鐘の音。その音は百八つ打たれます。ところで、この“百八“とは一体何を意味しているのでしょうか。

仏教の教えによると、人間は生きていく中で百八つの煩悩を抱えているとされています。煩悩とは、欲望や怒り、嫉妬、迷いなど、心を乱す感情や欲のことです。つまり、鐘を百八回つくことで、その一年の煩悩を一つひとつ清め、心をリセットして新しい年を迎えるという意味が込められているのです。

この百八の数字にも諸説があります。たとえば、「六根(眼・耳・鼻・舌・身・意)」×「六塵(色・声・香・味・触・法)」×「三毒(貪・瞋・痴)」=108という説、この“三毒”が、“過去・現在・未来”の時間軸になったり、“好・悪・平”の三種の感情に置き換えられた説、一年を表す十二ヵ月と二十四節気、七十二候を足した数が108になる説も。つまり、ただの“多い数字”ではなく、人間の心の構造を細分化して象徴的に表した深い意味があるのです。

ちなみに、野球の硬球(公式球)の縫い目は108本で、煩悩の数に由来すると語られがちですが、これはあくまで後付けの俗説。8の字型に裁断された2枚の革を赤い糸で縫い合わせる際に、投げやすさなどの実用面の最適解として導き出された結果が108針というものです。

また、除夜の鐘をつく行為自体にも興味深い効果があります。単に鐘の音を聞くだけでなく、自ら手を合わせ、心を込めて鐘をつくことで、体内の緊張がほぐれ、精神が落ち着くともいわれています。まさに“音の瞑想”ともいえる瞬間です。夜空に響く鐘の余韻は、寒さと静けさが重なって心に染み入り、日常の喧騒から離れた非日常体験を生みます。もし、大晦日の夜、近所や出掛けた先で除夜の鐘が聞こえてきたら、迷わず見に行きましょう。運が良ければ、鐘をつく体験ができるかもしれません。

ちなみに、日本人は音に敏感であるという説もあります。蝉の声や秋の虫、野鳥の鳴き声などを聞き分けられるのは、日本ならではの環境や文化が影響しているのではないか、と考えられているのです。これは科学的に完全に証明されているわけではありませんが、こうした背景から、除夜の鐘の音に心が洗われるような荘厳さを感じるのも、日本ならではの文化的感覚なのかもしれません。
年末に耳を澄ませば、どこからともなく聞こえてくる鐘の音。これを機に、除夜の鐘の意味を改めて考え、静かな気持ちで新年を迎えてみてはいかがでしょうか。百八つの鐘は、私たちの煩悩をやさしく流し、清らかな心で一年をスタートさせてくれる、そんな魔法のような存在なのです。
極上1.8L
兵庫県三木市吉川・口吉川 「嘉納会」特A地区産 山田錦100%使用。
生酛造りで醸した品格あふれる味と香りの本醸造です。

菊正宗ネットショップはこちらから
▼https://www.kikumasamune.shop/