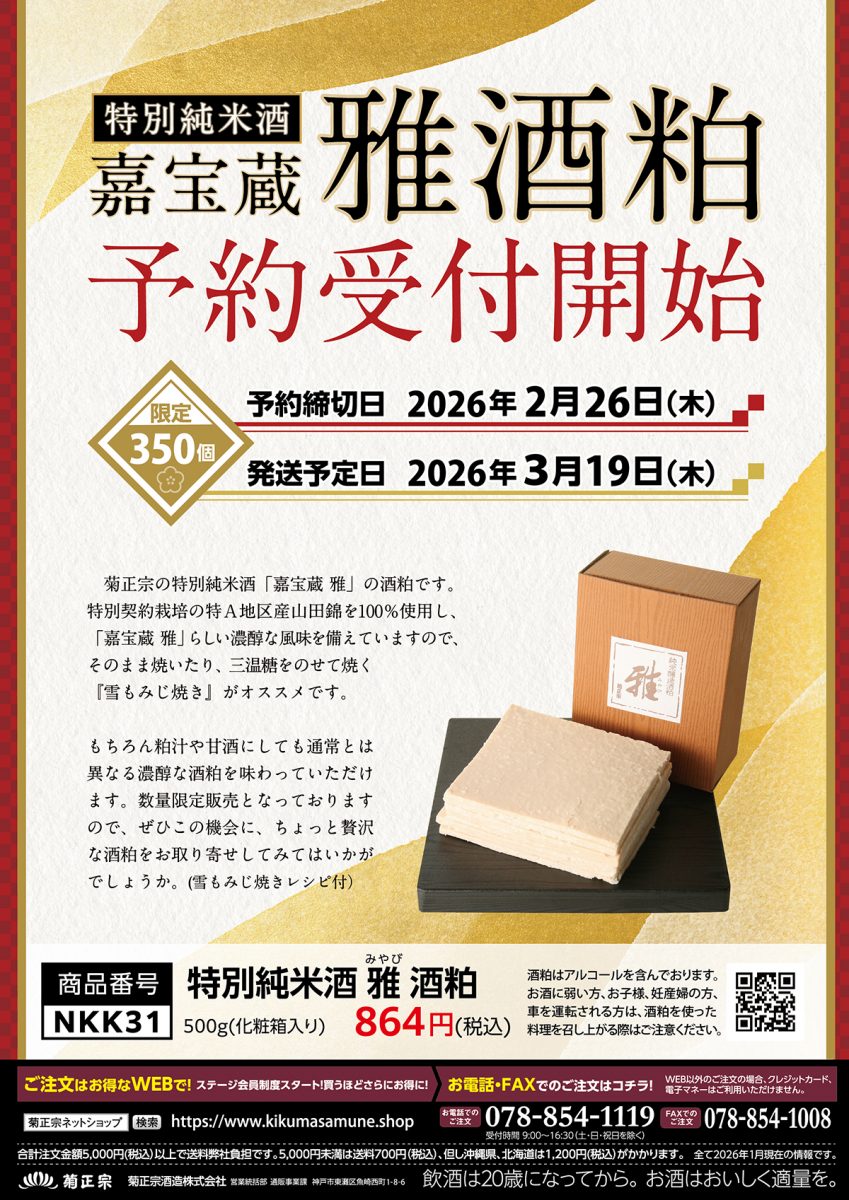主流のマダコとは異なる、さっぱりとした“冬ダコ”という存在。
世界的に見ても、日本ほど日常的にタコを食べる国は珍しいといわれています。北欧神話に登場する怪物「クラーケン」を連想させ、軟体で滑りのある見た目から「デビルフィッシュ」とも称されることもあるタコ。そうしたことから、海外で食文化として根づいている地域はイタリアやスペインなどの地中海沿岸を中心とした一部地域に限られています。しかし近年、訪日したインバウンド客がたこ焼きやタコの酢の物、タコの唐揚げなどのタコ料理を口にし、絶賛する声が聞こえるようになりました。

未知の食材だったタコが、日本の味付けと調理法によって“感動の一皿”に変わる…そこに、日本の食文化の底力が表れているのかもしれません。日本で流通する多くはマダコで、夏が旬。歯ごたえがよく、旨みのある定番のタコで、本州以南の沿岸、とくに瀬戸内海や九州で豊富に獲れます。兵庫県の明石だこ、神奈川県の佐島の地ダコなどのブランドマダコは高値で取引されるほどの絶品です。一方、北海道や東北エリアに生息するミズダコは大型のタコで、マダコとは旬が真逆の今の季節、冬です。マダコとミズダコで旬が真逆になるのは、なぜでしょうか。それは、タコはほとんど泳がず岩陰や海底に張り付く生息スタイルであるため、回遊せず、その場所の水温や環境に強く影響される“環境適応型”の生き物だからです。結果として、一番美味しくなる旬の季節が真逆になるということです。

ミズダコは、秋から初冬に産卵し、冬に身がのって旬を迎えることになります。寒い海で身が締まり、甘みと旨みが最高潮になるからです。ミズダコは名前の通り水分が多いタコですが、冬になるとその水分の中にしっかりとした旨みが宿ります。とくに吸盤の部分は、とろっとした舌触りと上品な甘さがあり、刺身で食べると“タコってこんなに甘かった?”と驚く方も少なくありません。繊維が細かいミズダコは、薄く切るほど口当たりがよくなり、噛むたびに甘みが広がります。皮目を軽く炙った“松皮造り”にすると、香ばしさも加わって冬らしい一皿になります。

合わせるなら、淡麗でキレのある純米酒や、軽く冷やした辛口の日本酒が相性抜群です。ミズダコのしゃぶしゃぶもおすすめです。昆布出汁にサッとくぐらせ、色が変わった瞬間が食べ頃。加熱しすぎると硬くなるので、あくまでサッとで。ポン酢やもみじおろしで食べると、ミズダコの甘みが一層引き立ちます。ここには、甘みのあるギンルビィの燗酒を合わせるのもいいですね。身体も心も温まります。酢味噌和えや“ぬた”も、冬のミズダコならではの一品です。吸盤のとろみと、酢味噌のコクが重なって、酒の肴として完成度の高い味わいになります。カラシを少し効かせると、ぐっと大人向けの表情になります。

煮物にしても、ミズダコは実力を発揮します。大根と一緒に炊くと、タコの旨みが出汁に溶け込み、家庭料理とは思えない奥行きのある味になります。マダコに比べて硬くなりにくいのも、ミズダコの強みです。素材の持つ旬の美味しさに、旨い酒を合わせる。それが、一番贅沢で、いちばん自然な楽しみ方なのかもしれません。

菊正宗だけの特別な酒米「兵庫恋錦」を使った「幻の酒」
酒米の王者・山田錦を親に持ち、その遺伝子を継承する幻の酒米・兵庫恋錦。
お米自体が柔らかくてデリケートなため、仕込みの難易度は高く、高度な技術を要します。
米一粒一粒を大切に精米し、手間ひまをかけて、菊正宗ならではの「幻の酒」を完成させました。
菊正宗ネットショップはこちらから
▼https://www.kikumasamune.shop/