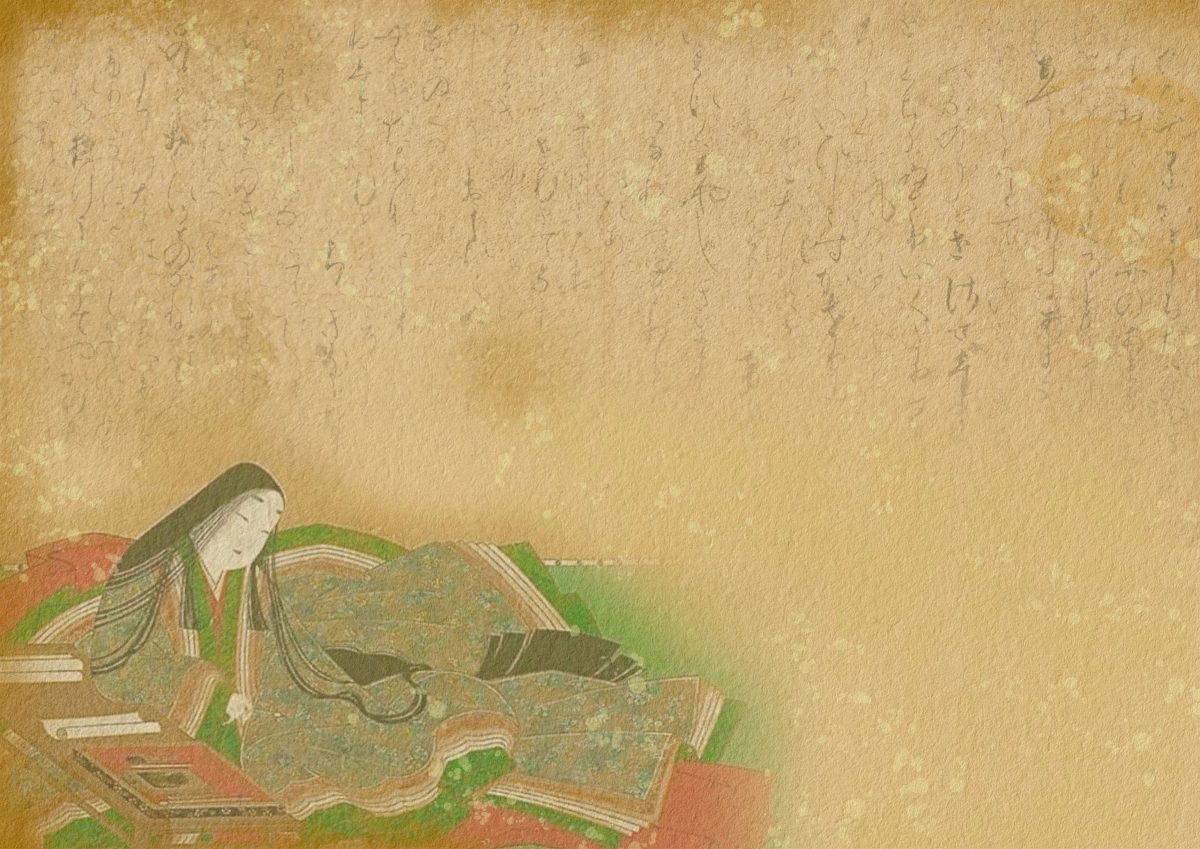ひと口に熱燗といっても、その旨さは、微妙な温度変化で異なります。
日中の肌がヒリヒリするような
秋特有の強い日差しも和らぎ、
冬の足音が聞こえ始めました。
とくに朝晩は冷え込み、
手足の冷たさが気になる季節です。
寒さが増した夕方、
店頭で目に映る秋冬野菜は、
まるで美味しい鍋料理へと
誘うように見えます。
夏に楽しんだ冷酒から
燗酒の温かさを求める
肌寒さが訪れたようです。

燗酒の魅力は、
身体をじんわりと内側から
温める心地よさだけでなく、
日本酒本来の味わいや香りを
引き立てるところにあります。
そして、燗酒の楽しみは
温度の違いによって
さらに広がります。
燗酒の適温は
酒質や料理により異なりますが、
好みによる影響が大きいです。
30℃の「日向燗(ひなたかん)」は、
口に含むと柔らかな優しい温度で、
香りが一層引き立ちます。

35℃の「人肌燗(ひとはだかん)」は、
ぬるく感じる温度ながら、
味わいが柔らかく膨らみ、
酒の旨さを引き出してくれるのが
特徴です。
さらに40℃の
「ぬる燗(ぬるかん)」になると、
芳醇な香りが広がり、
お酒の旨味が最大限に引き立ちます。
濃い味わいの料理ともよく合い、
鍋料理の相棒として人気の温度です。
45℃の「上燗(じょうかん)」は、
味と香りのバランスが良く、
しっかりとした旨味を感じられる温度。
お酒の風味が引き立つため、
濃厚な煮込み料理などと相性抜群です。
50℃の「あつ燗(あつかん)」は、
ギリギリ徳利を持てるほどの熱さで、
香りがさらに立ち上り、
寒い夜に飲むと
身体の芯まで温まる心地よさが魅力。
もっと熱い55℃の
「飛びきり燗(とびきりかん)」では、
シャープな香りとともに辛口のお酒が
キリッと引き締まり、
その奥深い味わいもひとしお。

温度による飲み方だけでなく、
最近では日本酒をベースにした
変わり種のアレンジドリンクも
注目されています。
日本酒を炭酸水で割る
「酒ハイボール」は、
爽やかな風味で食中酒としても
楽しめます。
また、熱燗に
少量の梅酒を加えた「熱燗梅酒」や、
柚子の皮を浮かべた「柚子燗酒」は、
甘酸っぱさや柑橘の香りが特徴で、
とくに若い世代に人気です。
少し変わったアレンジとしては、
日本酒にみかんやりんごなどを
加えて楽しむ「和風サングリア」も
面白いアレンジです。
酒税法違反になるので、
フルーツを漬け込むのではなく、
飲む直前に混ぜるのがポイント。
フルーツの風味が
もっと欲しい場合は、
ジュースを少し加えると
さらにフルーティーさが際立ちます。
さらに、
燗酒を出汁で割った「出汁割」も
若い層に人気だといいます。
最初は日本酒のお湯割だったものが、
味が薄まるとの理由から
出汁で割る旨さに気づいたようで、
おでん出汁がベストマッチ。

さらに簡単なアレンジは、
軽く炙ったイリコを1尾入れて
燗をつけるだけで、
日本酒の旨さに香ばしさが加わる
ヒレ酒と同じ原理です。
冬は、日本酒を
温度によって飲み比べたり、
アレンジレシピで楽しんだりと、
その可能性がぐんと広がる季節です。

寒さが本格化するこれからの時期、
日本酒のさまざまな魅力に触れながら、
心も身体も温まる特別なひとときを
過ごしてみてはいかがでしょうか。
季節限定のお取り寄せ
「とらふぐ 焼ひれ」

居酒屋の定番酒
「菊正宗 上撰720mL」

菊正宗ネットショップはこちらから
▼https://www.kikumasamune.shop/