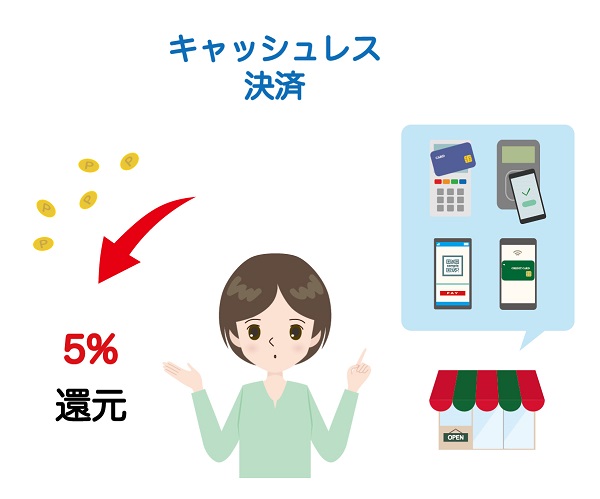少し複雑な「マイナポイント」。
参加には事前登録が必要です。
昨年10月にはじまった
「キャッシュレス・消費者還元」
事業が6月末で終了しました。
当初懸念された
キャッシュレス決済の利用ですが、
次第に需要が高まり、
コロナ禍の自粛期間中に
ネット通販を利用された方が
増えたことで、消費還元で
おトクに買い物ができた方も
多数いらっしゃったようです。
「マイナポイント」は本来、
政府が各省庁とともに推進する
消費刺激施策の一環でした。
経済産業省主導により
消費税増税対策として
導入された消費喚起を促す
「キャッシュレス・消費還元」事業が
6月末で終了後、7月から8月にかけて
オリンピック特需による
消費の高まりを経て、
9月から総務省による
「マイナポイント」事業へと
続く予定でしたが、
オリンピックの延期により、
少し長い助走期間を得たような
感があります。
とはいえ、「マイナポイント」も
家計にやさしいおトクな施策なので、
利用する、しないに関わらず、
エントリーだけはしておく
に越したことはありません。
さて、「マイナポイント」事業とは、
マイナンバーカード所有者だけが
申請できるポイント還元事業で、
この事業に参加している
キャッシュレス決済のひとつを選び、
エントリー。
実施期間の7ヵ月間に、
選んだキャッシュレス決済を
利用した現金チャージまたは
買い物に対して25%のポイント
(上限5000円相当)が還元
されるというものです。
ちなみに、「マイナポイント」
というポイントはなく、
各キャッシュレス決済の
“ポイント還元”の総称です。
- 〈マイナポイント事業の概要〉
- 申請受付:7月1日開始
(実施後も継続)
- ポイント還元実施期間:
9月1日〜2021年3月末までの
7ヵ月間
- マイナポイント事業への
エントリーの流れ
① マイナンバーカードの準備
(マイナンバーカードを
持っていない場合は、申請)
② マイキーIDの設定
(総務省の特設サイト)
③ 対象となるキャッシュレス決済
サービスの選択
(申請後の変更はできない)
④ 登録完了
- 「マイナポイント」の
登録手続き完了後、
実施期間内に登録した
キャッシュレス決済サービスを利用
- 後日、利用額の25%分
(最大5000円分)
のポイントが、登録した
キャッシュレス決済サービス
のポイントとして付与される

「マイナポイント」を賢く利用するために。
「マイナポイント」事業に
エントリーするためには、
少し複雑な手続きを要します。
余裕を持って
申請作業を行うことが大切です。
- 〈マイナポイント利用の注意点〉
マイナンバーカードの普及促進
という側面があるため、
マイナンバーカードの取得
が前提条件です。
まだ取得されていない方は、
早く申請しましょう。
取得に要する時間は
約1ヵ月が目安。
混雑が予測されるため、
2ヵ月かかる場合もある
のでご注意を。
スマホからの申請が便利です。
なお、マイナンバーカードの
取得に時間がかかって、
実施期間にかかっても
申請は可能なので、
ご安心ください。
- ポイント付与全体の予算は2000億円。
5000円で割った場合の
先着枠は4000万人で、
予算上限に達した時点で
締め切られるとのこと。
ネット情報では、
エントリーを締め切られる前に
早期申請を薦めるサイトと、
新しいキャッシュレス決済
サービスの参入を待つことを
薦めるサイトに二極化。
ここは自己判断です。
- キャッシュレス決済サービス
の選択にあたっては、
5000円にプラスして
各サービス独自の
付与が期待できます。
ネット通販の利用機会が多い方は
“○○ペイ”に代表される
キャッシュレス決済、
日々の買い物利用の方は
プリペイドの“電子マネー”
が使い勝手か良いようです。
ちなみにキャッシュレス決済は
決済時点、プリペイドの場合は
チャージ時点がカウントのタイミングです。
- マイナンバーカードは
子どもにも発行されるので、
ひとつにまとめて申請が可能です。
たとえば4人家族の場合、
最大20000円分のポイント付与
が受けられることになります。
利用する人にとって
ベストなキャッシュレス決済
を選ぶことが
大切なポイントといえます。

菊正宗では、
ただいまご使用いただける
キャッシュレス決済の導入
に向けて準備中です。
準備が整い次第、
詳細をご案内させて
いただく予定なので、
ご期待ください。