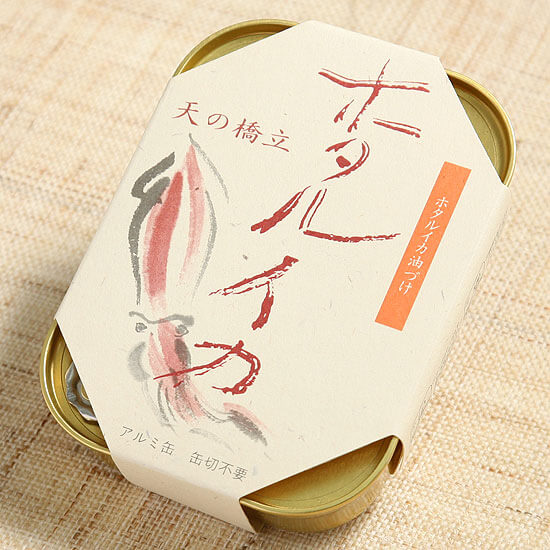丁寧な下ごしらえで、「あさり」の旨味を最大限に引き出すこと。
「あさり」は、3月から4月にかけて、
美味しい旬の時期を迎えます。
この時期は、
「あさり」の繁殖期にあたり、
産卵のために
栄養を身体に蓄えているため、
身がより大きく肉厚で、
豊かな旨味を楽しめる時期なのです。
毎年、潮干狩りのシーズンは、
この春の産卵期とともにやってきます。
また、関東以南に生息する
「あさり」は、
秋にも産卵期を迎えるため、
9月から10月にかけても
旬の味覚に数えられる
珍しい生態を持っている二枚貝です。
「あさり」は海水温が
20〜25℃になったあたりで
繁殖を開始します。
ところが、この温度がずっと
続いているときに繁殖は始まりません。
つまり、水温が急激に変化する
春と秋に繁殖状態になるというもの。
カラダを取り巻く温度変化が
キッカケとなって
敏感に反応し始める現象は、
桜が開花する“休眠打破”と
似ています。
ちなみに、「あさり」が
もっとも美味しいのは
繁殖直前の栄養を蓄えている
旬前半の時期とのこと。

さて、「あさり」を調理する前の
下準備は、かなり大切です。
ここで手を抜いてしまうと、
料理の仕上がりに
大きく影響を与えてしまいます。
その大切なポイントは “砂抜き”と
“ストレスを与える”の2つです。
まずは“砂抜き”。
スーパーなどのお店で購入した
「あさり」は、出荷前に
表面を洗ってあるので、
サッと水洗いする程度でOK。
その後、塩水にひたひたに浸して、
貝が生息している海の底の
暗い環境に合わせるために
新聞紙をかぶせ、約1時間。

潮干狩りで獲ってきたものは
表面が汚れているので、
貝をこすり合わせるように水洗いし、
同じように半日ほどおきます。
このときに浸け込む塩水は、
海水の塩分濃度に近い3%が最適。
これ、意外と大切なポイントです。
500㎖のペットボトルにキャップ2杯分
の塩(約15g)を加えるのが約3%の
濃度の目安なので、ご参考に。
素早く砂抜きをしたい場合は、
薄いパッドに「あさり」を並べて
50℃前後のお湯に浸すと
約15分前後で砂を吐かせる
時短方法もありますが、
その美味しさを
最大限に引き出すためには、
余裕を持った下ごしらえがオススメ。
この方法は、あくまでも
急いでいるときに利用ください。
続いて“ストレスを与える”です。
砂抜きが終わった「あさり」は、
すぐに調理したり、
冷蔵庫に入れて保存しがちですが、
このタイミングで、
浸っている水を抜いて、
少し濡らしたキッチンタオルをかぶせ
20℃前後の室温で3時間ほど
放置するのがポイント。
水を抜かれた「あさり」は
エラ呼吸ができなくなるため、
そのストレスから体内の
グリコーゲンをエネルギー源にして
生き延びようとします。
そのときに増加するのが
旨味成分の“コハク酸”。
ストレスを感じれば感じるほど
美味しさが増すというもので、
「あさり」の下ごしらえは、
これで完了です。

素材の旨さを味わうなら、まずは「あさりの酒蒸し」。残った煮汁は味噌汁に。
素材として「あさり」の
美味しさが引き出せたところで、
「あさり」の旨味を十分に
堪能するなら、「酒蒸し」がベスト。
これだと「あさり」の
シンプルな旨味をストレートに味わえ
何より調理が簡単なのが魅力です。
下処理の終わった「あさり」を
フライパンに並べ、
「あさり」が1/3ほど浸るまで
日本酒を回しがけ。
中火でコトコト、
浸した日本酒が沸くまで待ちます。
沸いたら蓋をして約2〜3分蒸し煮に。
「あさり」の口が開くのが、
ちょうど食べ頃サイン。
器に盛り付けて
小口切りのネギを振りかければ、
後は美味しくいただくだけ。
「あさり」の塩味があるので
調味料は不要ですが、
物足りないようであれば、
ひとつまみの塩をパラリと加えて
味の調整を。
「あさり」を食べた後の煮汁には
「あさり」エキスがたっぷり
溶け込んでいるので、
煮汁を捨てずに味噌汁に利用、
その美味しさを
もう一度味わってみましょう。
「あさりの酒蒸し」をつくる場合、
日本酒で蒸すのには理由があります。
まずは、貝特有の生臭さを
和らげる効果。
アルコールが蒸発する際の
共沸効果によって食材の臭い成分を
一緒に取り除くとともに、
お酒に含まれている有機酸によって、
素材の臭みを消してくれます。
また日本酒に含まれている糖類や
アミノ酸は加熱されることで、
上品な香りや風味を加える効果が
高いとされ、プロの和食料理人は
少なからず、この効果を上手く調理に
生かしています。
また、日本酒には食塩が
含まれていないため味がよくしみ込み
日本酒に含まれている糖分が、
タンパク質や水分と結びついて
食材をやわらかくします。
塩が含まれている料理酒の場合は、
塩の浸透圧によって
水分が外に抜け出して、
逆に食材がやや硬くなります。
今が旬の「あさり」の美味しさを
ストレートに楽しむのなら
「あさりの酒蒸し」が最適。
うまい日本酒と一緒に
春を楽しみましょう。
残った煮汁は、翌朝の味噌汁に。
二日酔い気味の身体を、
シャッキリと整えてくれます。