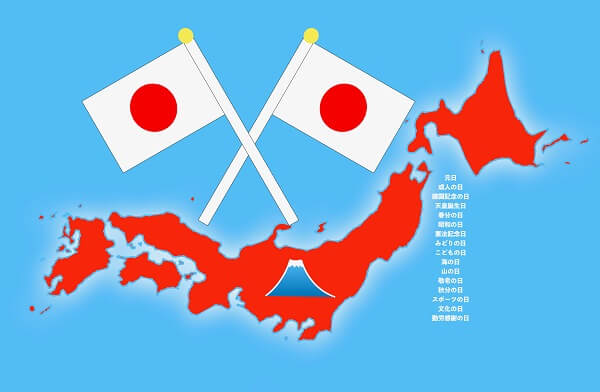12月の別称は、「師走」だけじゃない。風流で粋な表現をご紹介します。
12月になった辺りから
街で聞こえ始める
“もう年末、1年が経つのは早いね”
という言葉。
12月ならではの風物詩ともいえます。
歳をとればとるほど、
1年の短さを実感するのは、
以前にここで紹介した
“ジャネーの法則”で
解き明かすことができます。
50歳の人にとっての1年は
生涯の1/50程度の長さですが、
5歳児にとっては
人生の1/5に感じるという
心理的な感じ方の法則です。
つまり、
5歳児にとっての1年は、
50歳の人が感じる1年の
10倍相当の長さに感じる
ということです。
さて、旧暦の各月を
睦月、如月、弥生…
と数字以外の呼称で呼ぶのを
“和風月名(わふうげつめい)”
といい、現代の数字表記とは
即座に一致しづらい感もあります。

そんななか、
“12月イコール「師走」”
の認知度はとりわけ高く、
もはや一般常識レベルといっても
過言ではありません。
これは、年末になると
テレビなどで「師走」という言葉が
多用されることも
大きく影響しているといえます。
この“和風月名”の起源はかなり古く
日本最古の書籍「日本書紀」には、
2月が“きさらぎ”、4月が“うげつ”
という表記が登場します。
もともと
古代中国から伝わった暦の概念で、
中国月の呼び方で、
2月を如月、5月を皐月、と
“和風月名”と同じ漢字表記が
使われてはいますが、
“和風月名”は
日本独自の呼称のようです。
この「師走」以外にも
梅初月(うめはつづき)、
春待月(はるまちづき)、
三冬月(さんとうづき)、
極月(ごくげつ/きはまりづき)、
窮月(きゅうげつ)、
除月(じょげつ)、
弟月(おとづき/おととづき)、
限月(げんげつ)、
臘月(ろうげつ)など、
実にさまざまな呼び名が。
これらは宮中の歌会で
歌を詠んだ際に、
風流で粋な表現を用いた
名残なのかも知れません。
また、この時期によく使われる
“年の瀬”という言葉があります。
江戸時代頃から
使われ出した言葉です。
ここでいう“瀬”とは、
川の流れが急なところを指す言葉で、
年末に向けて差し迫った
慌ただしい様子を表す言葉として、
こちらも定着しています。

「師走」の語源、私たちが知っている以外の諸説が盛りだくさん。
「師走」という言葉について、
その由来とされているのが
“師馳す(しはす)”です。
12月にお経を読むために
僧侶(師)があちらこちらの家に
馳せ参じている目まぐるしさを
表した言葉といえます。
つまり、“師が馳せる月”が
“師馳す”に転じ、
“馳す”に“走”をあてたもの。
これは平安末期に編纂された
「色葉字類抄
(いろはじるいしょう)」
で紹介された説で、
この語源が、一般的には定着し、
有力とされています。
この語源以外に、
1年の終わりとなる最終月で
年が果てるということを意味する
“年果つ(としはつ)”が変化した
という説があります。

また、同じく1年の終わりの月
ということで四季が果てる月を
意味する“四極(しはつ)”を
語源とする説、
さらに、
1年の最後になし終える
という意味を持つ
“為果つ(しはつ)”
が転じたとされる説、
“成終月(なしはつるつき)”
の略語説、
農作業が終わり、年貢の新穀の
“飲果月(しねはつるつき)”
という説、
稲のない田んぼの様子を表した
“し干あす”説、
“忙し(せわし)”説、
“暫し(しばし)”説など、
紐解いていくと数多くの語源が存在。
そして、現代に当てはめた、
年末に忙しく走り回る
学校の先生の様子を表している言葉
として説明されることもあるようです。

この時期だけの限定出荷で
好評だった純米大吟醸「嘉宝」が、
デザインも一新して12月1日から
通年販売解禁に。
今回から
火入れ回数を減らしているので、
よりフレッシュな美味しさを
お楽しみいただけます。
今年も残すところあとわずか。
やり残したことがあるならば
早目に済ませて、
余裕のある年越しを。
新しい「嘉宝」で、
お楽しみいっぱいの年越し準備を
お忘れなく。