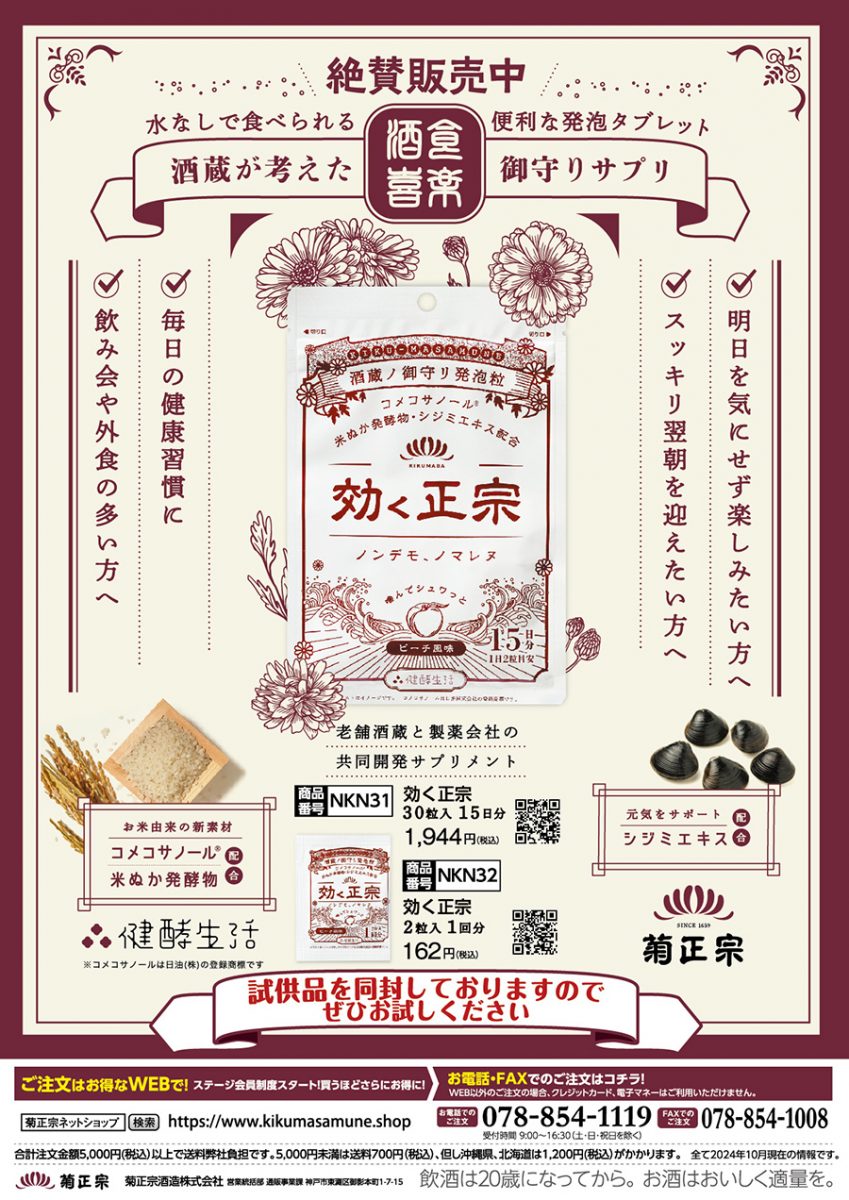昔から、銭湯はコミュニケーションの場。“銭湯で整える”が新しいトレンドです。
10月10日は「銭湯の日」です。
1991年(平成3年)、
全国浴場組合連合会が
銭湯文化の普及をめざし、
銭湯を
より多くの人に親しんでもらおうと
制定しました。
この日が「銭湯の日」となったのは、
“1010(せんとう)”
という語呂合わせからです。
また、1964年(昭和39年)の
東京オリンピックの開会式が行われた
10月10日が「体育の日」と
定められたことにも由来しています。
このオリンピックをきっかけに、
日本ではスポーツが奨励され、
スポーツで汗を流した後に
銭湯でさっぱりと
リフレッシュするという意味が
込められた日でもあります。

日本の入浴文化のルーツは、
奈良時代の仏教伝来にまで遡ります。
仏教寺院の湯屋(ゆや)は、
心身ともに清めるための場として
使われていました。
現在の銭湯に近い公衆浴場が
庶民に広まったのは江戸時代です。
江戸の急激な人口増加と、
火災リスクを回避するために、
密集する木造家屋では
個人の風呂を持つことが
難しかったため、
公衆浴場が誕生しました。
ここは、
体を清潔に保つ場所だけでなく、
社交場としての役割も
果たしていました。

江戸初期には
男女混浴が一般的でしたが、
江戸後期には
道徳的な考えから混浴が規制され、
男女別の浴場へと変わっていきます。
知らない者同士が
裸でお湯に浸かるという
独特の銭湯文化はこの頃に確立され、
現代にも引き継がれています。
ちなみに、武士にとって刀は
片時もその身から放さない
大切なものでしたが、
“風呂には刀を持ち込まない”
という暗黙のルールがあり、
武士といえども風呂に入る時だけは、
番台に刀を預けたとのことです。
戦後の復興期には、住宅事情も悪く、
多くの人々にとって銭湯は
生活に欠かせない施設でした。
しかし、1970年代に入ると
住宅に浴室が備えられるようになり、
トイレと風呂が一体化した
ユニットバスの登場により、
銭湯の需要は一気に減少。
最盛期には
約25,000軒もあった銭湯は、
現在2,000軒ほどに減少しています。

一方で、最近では
訪日外国人観光客の間で
銭湯が再び注目を集めています。
日本観光の定番ともいえる
人気の東京や京都、大阪の混雑を
避ける観光スポットとして
密かに注目され始めたのが
全国各地の温泉です。
昔は、
知らない人と裸で入るお風呂に
抵抗のあった外国人も、
日本文化に好意を持ち、
そのひとつの温泉に挑戦。

湯船に浸かるリラックス効果や
露天風呂の開放感など、
その癒し体験の虜に
なっていきました。
その感動をSNSを通じて
発信し始めたことから
日本の温泉が話題になり、
その影響で、都会で
温泉のような感動体験ができる銭湯に
注目が集まり始めているようです。
また、
SNSに敏感な日本の若者の間でも
銭湯通いが新たなトレンドとして
加わりました。

サウナブームに続いて、
銭湯でのリラックス体験が注目され、
銭湯文化が新たな世代にも
受け継がれようとしています。
長い歴史を持つ銭湯文化は、
現代にもその価値を保ち続け、
未来へと継承されていくことに
なりそうです。